|
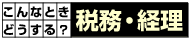
平川税務会計事務所 佐々木京子
第9回
直接償却と間接償却
不良債権の直接償却
不良債権の処理方法には直接償却と間接償却とがあります。
直接償却とは貸借対照表から不良債権を完全に切り離すことで、主として債権の回収、債権の放棄をいいます。
債権の流動化・証券化も直接償却の方法ですが、我が国では不良債権の市場が未成熟なため、処理策としては、今のところあまり機能している状況にありません。
債権の放棄による貸倒損失
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、書面により明らかにされた債務免除額は貸倒損失として、損金の額に算入することが認められています。(法基通9-6-1)
但し、上記要件を満たさない債権の放棄は、子会社等を整理する際の損失負担(法基通9-4-1)にあたる場合を除いては寄附金と認定され、損金算入に限度額が設けられています。
現在政府は大手銀行に対して、この直接償却の早期促進を要請しており、この7日には「私的整理に関するガイドライン研究会」が発足、今後の動きが見守られるところです。
不良債権の間接償却とは
間接償却とは、帳簿上は不良債権を残したまま、将来の損失に備えて、貸倒引当金を設定するものです。
貸倒引当金
金銭債権の貸倒見込額として、損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、繰入限度額までは損金の額に算入されます。
平成10年度の税制改正により、それまでの債権償却特別勘定は廃止され、金銭債権を以下の2つに分類して繰入限度額を算定することとなりました。
(1) 個別評価する金銭債権…その一部に貸倒れ等が見込まれる金銭債権
(2) 一括評価する金銭債権…(1)を除く売掛金、貸付金その他の金銭債権
なお、上記(1)については、平成13年度の税制改正により、その個別評価金銭債権に係る債務者ごとの繰入限度額に基づき、損金算入額を計算することとされました。
バックナンバー
(2001.6.18 ビジネスメールUP!
166号より
)
|

