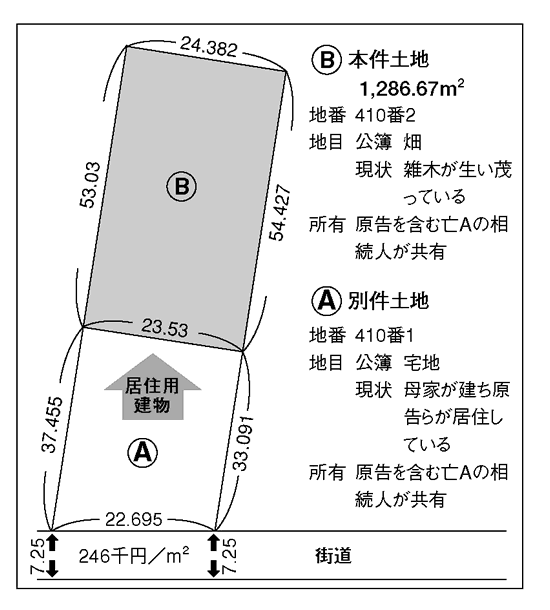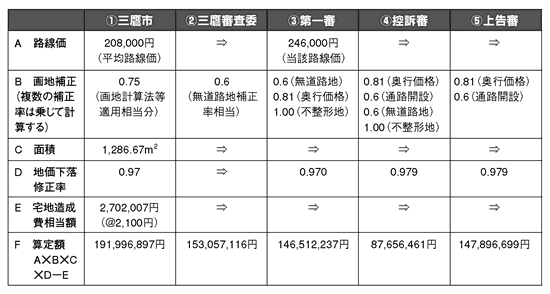|
無道路地に通路開設補正は適用なし
自己所有地を通路として使用している「無道路地」の評価が争点
最高裁判所第二小法廷(津野修裁判長)は平成19年1月19日、東京都三鷹市の市街化区域農地の固定資産の登録価格を争点とする審査決定取消請求上告事件において、「本件土地の評価に当たっては、取扱要領に従い、通路開設補正を適用しないで評価すべきものである。」などと判示し、通路開設補正の適用により登録価格を大幅に引き下げた控訴審の判断を斥け、三鷹市固定資産評価審査委員会の決定価格から3.4%程度引き下げた価格(1億4,789万6,699円)を超える部分を取り消す判決を言い渡した。
本件上告審の事案の概要
本件については、控訴審判決について、本誌79号14頁で解説を試みているので、その解説に付した土地の利用図面を再掲する。固定資産の登録価格について争われているのは、本件土地(B部分、網かけ)についてである。街道に接道した別件土地(A部分)と同一の所有者が所有しており、別件土地には、居住用の建物が建てられている。本件土地は路線に接しておらず、本件土地への出入りは別件土地を利用して行われている。本件土地と別件土地は、垣根等で区分されている。
本件土地は、公簿・現況の地目がいずれも畑であり、地方税法に規定する市街化区域農地に該当する。
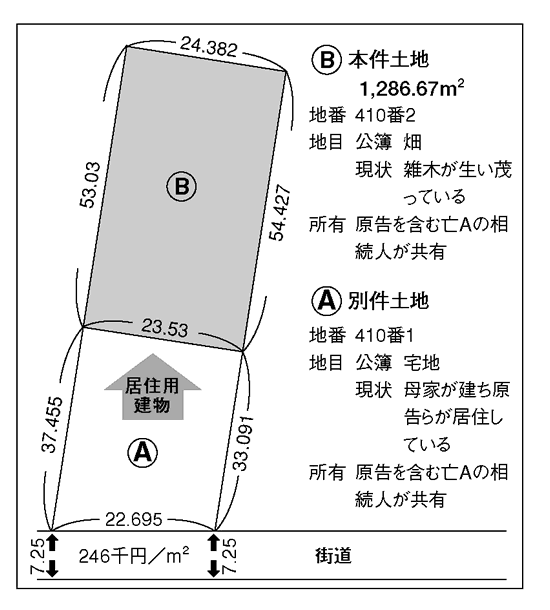
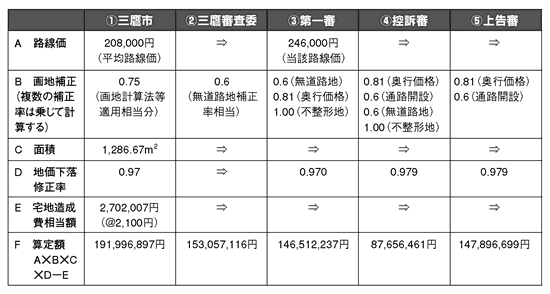
固定資産評価審査委員会が「無道路地」とは何か? で上告
控訴審の判断は、本件宅地について、通路開設補正率と無道路地補正率を併せて適用していることに特徴がみられる。控訴審は、「評価基準上、本件土地を一つの画地として評価する場合には、その利用に当たって道路の開設が必要となることは、これに接して同一の所有者の土地があるか否かにかかわらないというべきであり、道路の取得、開設費用が架空の費用であるなどとはいえない。(中略)事実上、同一所有者の土地を利用して街路への通路としている場合につき、通路開設補正率の適用自体を否定することは、評価基準の想定する所要の補正の範囲を超えるものというべきであり、通路開設補正率の適用自体を否定して行う評価は、その限度で評価基準に従った評価とはいえないと解すべきである。(中略)評価基準の定める画地計算法に従って評価する場合、本件土地については、通路開設補正率0.6を適用するのが相当であるというべきである。」と判示していた。
控訴審判決に対し、三鷹市固定資産評価審査委員会は、上告受理申立理由書において、「本件土地は、確かに公図上は道路に接していないが、所有者を同一にし、かつ道路に接している別件土地を利用して自由に出入りしているという実際の利用状況からすれば、本件土地は、評価基準上の「無道路地」には含まれないというべきことになる。」・「市街化区域農地に画地計算法を適用する場合、宅地と異なり、補正項目の一部を適用しないこと等が許容される。」と主張した。
最高裁判所は上告審として受理し、平成18年12月11日に口頭弁論が開かれた。
通路を確保する費用・期間は要しない
津野裁判長は、以下のように判示し、通路開設補正の適用を斥けた。
「通路開設補正率は、当該無道路地が公路に接続しない状態を解消するための通路を確保するのに必要な費用及び期間に着目した補正率であると解される。そうすると、現に自己所有地を通路として使用し、これによって公路に接続している土地は、たとえ公図上は公路に接していなくとも、新たにこれを公路に接続させる通路を確保するための費用及び期間を要しないのであるから、通路開設補正を適用しない取扱いをすることも許されるものと解するのが相当である。したがって、取扱要領が上記のような土地について通路開設補正を適用しないものと定めていることには合理性があり、この定めが評価基準に反し違法であるということはできず、本件土地の評価に当たっては、取扱要領に従い、通路開設補正を適用しないで評価すべきものである。」
※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
⇒著作権等について
T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
キーワード 「道路」⇒189件
(週刊「T&A master」196号(2007.1.29「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2007.2.26 ビジネスメールUP!
955号より
)
|