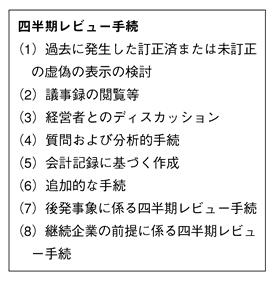|
�@
����20�N4��1������K�p�̎l�������r���[�����w�j����������
��v�m����A�l�������r���[���̕���Ȃǂ����\
�@���{���F��v�m�����10��30���A�č��E�ۏ؎����ψ����83����l�������r���[�Ɋւ�������w�j������\�����i�����͓�����̃z�[���y�[�W�������\�j�B����20�N4��1���Ȍ�J�n���鎖�ƔN�x���ɌW��l�����������\������l�������r���[�����{����邪�A���̊č���̗��ӓ_��l�������r���[���̕���A�o�c�Ҋm�F���̋L�ڗ�Ȃǂ������Ă���i�{��228���A229���Q�Ɓj�B
��1�l�������r���[�葱�J�n�O�Ō_��K�v
�@�܂��A�|�C���g�ƂȂ�̂��l�������r���[�_��̒������B�l�������r���[�ɂ��ẮA�N�x�̍������\�̊č��l�Ɠ���̊č��l���s�����ƂɂȂ邽�߁A�č��_��Ɠ����Ɏl�������r���[�̌_���������邱�Ƃ��\�ł���Ƃ��Ă���B
�@���ɑ�1�l������v���Ԗ����́A�O�N�x�̍������\�̊č��I����ɓ������邽�߁A��1�l������v���ԂɌW��l�������r���[�葱�J�n�O�Ɍ_����e�ɂ��č��ӂ��Ă����K�v������Ƃ��Ă���B
�N�x�č��̏d�v���̊�l�����
�@���̃|�C���g�͏d�v���̊�l���B������A�l�������r���[�́A�N�x�̍������\�č���O��Ƃ��Ď��{�������̂ł��邽�߁A�l�������r���[�ɌW��d�v���̊�l�ɂ��Ă��A�N�x�̍������\�č��ɌW��d�v���̊�l��K�p���邱�Ƃ������I�ł���Ƃ����B���̂����ŁA���Ȃ��Ƃ��A�N�x�̍������\�č��ɌW��d�v���̊�l������Ƃ��ׂ��Ƃ��Ă���B�N�x�̍������\�č��ɌW��d�v���̊�l�����ꍇ�ɂ́A�N�x�̍������\�č��ɂ����Ċe�l�����̎���⊨��ɂ��čs���ׂ��č��葱��K���ɂ����ʓI�Ɏ��{���邱�Ƃ��v��ł��Ȃ��Ƃ��Ă���B
�O���ƔN�x�̌p����Ƃ̑O��̋^�`�ɗ���
�@�l�������r���[�́A����A���͓I�葱���̑��̎l�������r���[�葱�Ɍ��肳��Ă��邪�A�����w�j�ł́A��̓I�Ȏl�������r���[�葱�ƂȂ�8���ڂ������Ă���i���L�Q�Ɓj�B
�@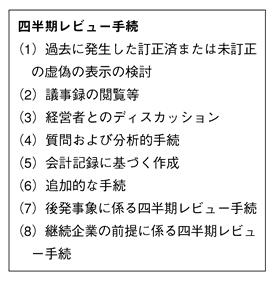
�@���̂����A�i6�j�̒lj��I�Ȏ葱�́A���₨��ѕ��͓I�葱���̎l�������r���[�葱���s�������ʁA�č��l���l�����������\�ɂ��āA��Ƃ̍�����ԁA�o�c���т���уL���b�V���E�t���[�̏��d�v�ȓ_�ɂ����ēK���ɕ\�����Ă��Ȃ����������݂���\���������ƔF�߂���ꍇ�A�܂��͋^�`���������ꍇ�ɍs�����̂ł���Ƃ��Ă���B���Ƃ��A�d��Ȕ������Ɋւ��Ĉ�ʂɌ����Ó��ƔF�߂���l�����������\�̍쐬��ɏ������Ă��邩�ǂ����ɂ��ċ^�`���F�߂�ꂽ�ꍇ���Y������B
�@�܂��A�i8�j�̌p����Ƃ̑O��ɌW��l�������r���[�葱�ɂ��ẮA���ɑO���ƔN�x�̌��Z���ɂ����Čp����Ƃ̑O��ɏd�v�ȋ^�`��������鎖�ۂ܂��͏ɑ傫�ȕω�������ꍇ�̌����ɍۂ��ẮA���������������łȂ����Ȃ��Ƃ�1�N�Ԃɂ킽�鎖�Ɗ����̌p�����Ɋւ��Ďl�����������\�̍쐬��ɏ������ēK���ɕ\�����Ă��Ȃ��ƐM�������鎖�����F�߂��邩�ǂ����ɂ��Č������邱�ƂɂȂ�B
�d�v�Ȏq��Г��̏ꍇ�͉����������{
�@���̂ق��A�q��Г��ɑ���l�������r���[�葱�ł́A�d�v�Ȏq��Г��̏ꍇ�ɂ́A�������邩���̊č��l�𗘗p���āA����A���͓I�葱�������{����B����A�d�v�Ȏq��Г��ɊY�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�e��Ђɂ����Ď���A���͓I�葱���𒆐S�Ɏl�������r���[�葱���s�����ƂɂȂ�B
�@���ɏd�v�Ȏq��Г��Ƃ́A�@�����K�͂̉�Ёi���㍂�\�����A���Y�\�����A�A����]���\����������݂đ����K�͂ƔF�߂���ꍇ�j�A�A�d�v�ȋ��U�\���̃��X�N�̒��x�������ƕ]��������Ёi���@�I�ȃf���o�e�B�u������s���Ă���ꍇ�A�O�N�x�܂��͑O�l�����ɏd�v�ȋ��U�̕\�����������ꂽ�ꍇ�A�d�v�ȋ������ۓ�������ꍇ�A�p����Ƃ̑O��ɏd�v�ȋ^�`��������鎖�ۂ�����݂���ꍇ�j���Y������B�܂��A����������Ђ̎��Ǝq��Ђ́A�ʏ�A���ɏd�v�Ȏq��Г��ɊY������Ƃ��Ă���B
�@�@��
�L���̖��f�]�p�△�f�g�p�͂��f�肢�����܂�
�@�@�����쌠���ɂ���
�@
�@ T&Amaster �ǎҌ���T�C�g
���������i���F�{���ɂ͓ǎ�ID�ƃp�X���[�h���K�v�ɂȂ�܂��j���h�c�E�p�X�̎擾���@
�@ �L�[���[�h�@��l�������r���[�v��40��
�i�T���uT��A master�v233��(2007.11.5�u���T�̃j���[�X�v���]�ځj
�i���ށF��v�@2007.12.19�@�r�W�l�X���[��UP!
1070�����
)
�@
|