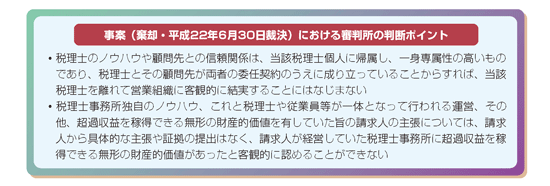|
審判所は一身専属性の観点から営業権を認めず
税理士業の事業承継、ノウハウや顧問先等は「営業権」に該当?
高齢化が進む税理士業界。高齢を理由に税理士事務所の事業承継を考えている税理士も少なくない。
顧問先や事務所全体を有償で事業承継する際、税理士が長年築きあげてきた事務所のノウハウや顧問先等を営業権として認識できるかどうかという疑問が生じるところだが、この点について、国税不服審判所は、税理士が築きあげてきたノウハウや顧問先等は営業権に該当しないとする旨の判断を行った事案を公表している(棄却・平成22年6月30日裁決)。本事案について紹介する。
税理士事務所の事業承継の際に「営業権」が認識できるか否か
今回紹介する事案は、税理士業を営む税理士(請求人)が同じ事務所に勤務する補助税理士へ税理士業を事業承継した際に受け取った金員が譲渡所得に該当するか否かが争われていたもの。請求人は事業を承継する補助税理士と「事業承継に関する覚書」を締結。覚書には、請求人が保有する顧問先や事務所の備品などを補助税理士へ有償で譲り渡す旨が明記されていた。
原処分庁は、税理士業務が一身専属性の業務であることから営業権の譲渡とは考えられないと主張したのに対し、請求人は、税理士、従業員税理士、従業員、顧問先と事務所独自のノウハウ等が一体となって税理士事務所が運営されていることに着目すれば営業権を認識することができると主張。事業承継の際、受け取った金員は営業権の譲渡対価であり、譲渡所得に該当するとしていた。
審判所は、営業権について、「企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊の製造技術及び特殊の取引関係の存在並びにそれらの独占性等を総合した、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係」をいうと指摘。そのうえで、本事案については、「税理士のノウハウ、顧問先との信頼関係は、当該税理士個人に帰属し、一身専属性の高いものであり、税理士とその顧問先が両者の委任契約の上に成り立っていることからすれば、当該税理士を離れて営業組織に客観的に結実することはなじまない」と判断。営業権の存在について、超過収益を稼得できる無形の財産的価値があったと客観的に認めることができないと結論付けた。
個別通達は営業権を認めず
税理士が得意先を他の税理士等に引き継いだ場合において、その引継ぎを受けた税理士から受け取る金銭の所得区分について、個別通達「税務および経理に関する業務の譲渡に伴う所得の種類の判定について」(昭42.7.27直審(所)47)は、税理士が、その業務を他の税理士等に引き継いだ対価として受け取る金銭等は、得意先のあっせんの対価であると明記。したがって、営業権の譲渡とは認めていない。
また、弁護士業の営業権が争点となった同様の事案(一部取消し・平成18年8月30日裁決)においても、審判所は、一身専属性の認められる弁護士業では、ノウハウ、依頼者との信頼関係等は弁護士本人に帰属し、弁護士を離れて営業組織に客観的に結実することはなじまないとし、一身専属性の観点から営業権は存在しないと結論付けた。
営業権の存在を立証できれば……
両事案とも「一身専属性」の観点から、営業権の存在が否定されている。ただ、営業権がすべて否定されるわけではない。税理士業を営む者が営業権を主張するためには、一身専属性以外の観点から、営業権の存在を立証する必要がありそうだ。
なお、財産評価基本通達上、税理士業に係る営業権は相続財産として評価する必要はない(メモ参照)。
memo
財産評価基本通達、税理士等に係る営業権は計上されず
相続税法基本通達10−6では、相続税法10条1項13号に掲げる「営業上の権利」には事業に関する営業権も含まれると規定しており、営業権を財産として取り扱っている。
しかし、財産評価基本通達165(営業権の評価)の注書きにおいて、「医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない」と定められている。税理士もこれに含まれることになり、税理士業を営む者の相続人は、被相続人が営んでいた税理士事務所の営業権を相続財産として評価する必要がないこととなる。
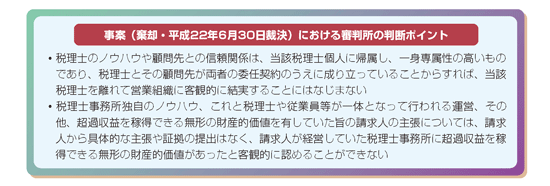
事業承継に伴い取得した金員、譲渡所得でなければ何所得?
税理士業の事業承継に伴い取得した金員が営業権の譲渡対価に該当しないのであれば、その金員がどの所得に区分されるかが問題となる。
前述の個別通達は、税理士がその業務を廃止するにあたり、従来関与していた得意先を他の税理士等に引き継いだ場合において、その引継ぎを受けた税理士等から受ける金銭等に係る所得はあっせんの対価であり、雑所得であると規定する。今回の税理士の事案において、審判所は、税理士(請求人)が受領した金員は営業権譲渡の対価には当たらず、顧問先等の取引先をあっせんした対価であり雑所得であると判断。個別通達と同様の判断を行った。しかし、弁護士の事案において審判所は、原処分庁の弁護士という事業に付随して得た収入、すなわち事業所得と解するのが相当であるという主張を認め、事業所得と判断した。
通達では雑所得だが、事業所得に該当する場合も
今回の税理士の事案では、請求人が当初から雑所得で申告を行っていたため、事業所得であっても雑所得であっても税額に変わりがなく、譲渡所得を否定した以上に所得区分の判断がなされなかった。しかし、一般論として、一部事業を承継させた者が営業譲渡後も事業を継続している場合には、譲渡対価は事業所得に含まれるようだ。
※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
⇒著作権等について
T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
キーワード 「営業権 税理士」⇒32件
(週刊「T&A master」394号(2011.3.14「SCOPE」より転載)
(分類:税務 2011.5.9 ビジネスメールUP!
1538号より
)
|