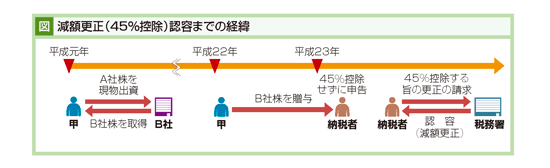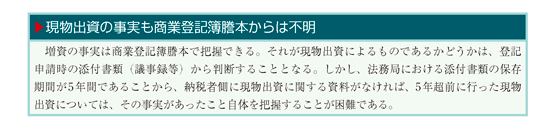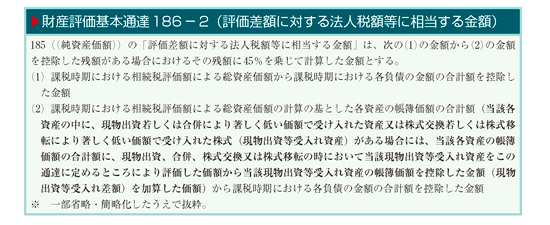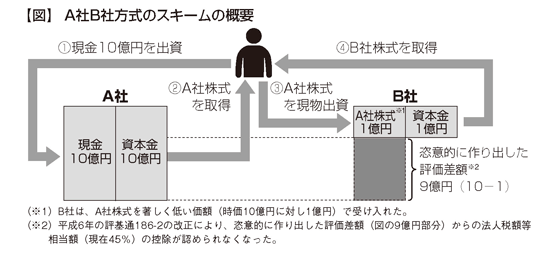|
評基通186−2の趣旨と異なる減額更正ケースが発生
帳簿類不存在で45%控除規制が形骸化
財産評価基本通達186−2は、現物出資等により著しく低い価額で受け入れた株式等がある場合、法人税額等相当額控除(現在45%控除)を規制する通達。バブル期などには、現物出資などを利用することにより、法人税額等相当額控除を恣意的にフル活用する租税回避策が横行し社会問題化、これらを規制する趣旨で平成6年に改正された。
ところが、この控除規制が実際に適用されない事案が発生した。現物出資を著しく低い価額で受け入れたことにより作り出された「含み益」を抱える典型的な株式の贈与事案だが、平成22年に贈与された株式の評価にあたっては、45%控除をまるまる行い、これが当局によって認められた。表面的には、評基通186−2の法人税額等相当額控除規制の趣旨と異なる処分に見えるが、これは、現物出資(平成元年)から課税時期(平成22年)まで既に21年が経過しており、「著しく低い価額での現物出資による受入れ」を証明する帳簿類の“不存在”が招来させたものといえる。
評基通186−2は、過去のどの時点の現物出資であっても制限なく適用されるが、現実の課税処分の射程には帳簿類不存在という限界があることを露呈した形であり、課税当局もこの時間的限界には問題意識を持っている。バブル期を中心に横行した租税回避スキームは、件数・金額ともに巨大であったし、現在「塩漬け」にされているその含み益が、今後発生する相続・贈与によって確実に表面化する。今回の処分が同様事案に及ぼす影響は計り知れない。
通達趣旨と異なる処分、恣意的な評価差額から45%控除を認める
今回取材により明らかになった事案の概要は次のとおりである(図参照)。
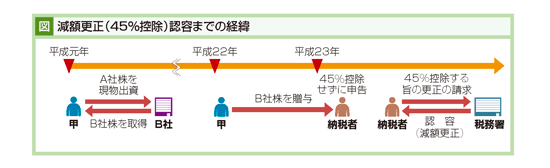
平成元年、A社株式(非上場)をもつ甲は、A社株式を非上場のB社へ現物出資し、B社株式を取得。B社は、A社株式を現物出資時の相続税評価額の6%程度の価額(著しく低い価額)で受け入れており、この結果、相続税評価額が数億円程度圧縮されることとなった。
平成元年時の帳簿類は存在しない状況
その後、様々な株価変遷があったものの、平成22年、甲からB社株式を贈与された納税者は、B社保有のA社株式について、現物出資により著しく低い価額で受け入れた「含み益」から45%控除をしない旨記載した贈与税の申告書を平成23年に提出した。
同年、納税者は、前述の「含み益」から45%控除をする旨記載した更正の請求を行ったところ、税務署長はこれを認容し、減額更正を行った。
なお、平成元年時(現物出資時)のA社に係る法人税申告書等は、法律上の帳簿保存義務が過ぎたこと等により納税者側で既に破棄されていた。
帳簿類不存在が大きな要素に
本来であれば、財産評価基本通達186−2(以下、「評基通186−2」という)の適用にあたり、前述の「含み益」から法人税額等相当額を控除することは認められないはずである。しかし、今回の事案は、法人税額等相当額を控除する旨の申告が税務署長から認容されたという注目すべきものである。
本誌の取材によると、現物出資時の法人税申告書等の帳簿類がないために評基通186−2の45%控除規制が事実上機能しないという問題が浮かび上がってきた。
会社法(旧商法)でも帳簿保存期間は10年
評基通186−2の適用にあたり、現物出資により受け入れた取引相場のない株式の現物出資時の相続税評価額を算定するためには、その株式発行会社に係る現物出資時の法人税申告書等の帳簿類が必要となる。
しかし、法律上の帳簿保存義務期間については、法人税法上は7年、会社法上(旧商法上)でも10年と規定されている。20年以上前に現物出資が行われたことを考えれば、ほとんどの帳簿類は破棄されており、逆に保存しているケースの方が稀であるといえる。
帳簿類がなければ時価の算定は困難
課税当局は、納税者側が評基通186−2に従った申告をする際には、帳簿類がない場合でも「何らかの方法で現物出資時の相続税評価額を把握していただきたい」としているが、現実問題として、現物出資時の帳簿類がなければ、納税者側で現物出資時の相続税評価額等を算定することは極めて困難となる。
一方、課税当局側の法人税申告書の保存期間は原則7年とされている。20年以上前の帳簿類が保存されていることも考えづらく、納税者だけでなく、課税当局側においても帳簿類が“存在しない”可能性が高いわけだ。
保存義務が過ぎたことなどにより帳簿類がないケースについて、課税当局側が現物出資等受入れ差額を認定する更正処分ができるかという点については、「個別事案の状況に応じて評基通186−2が適用できるかどうかを判断する」という回答だ。
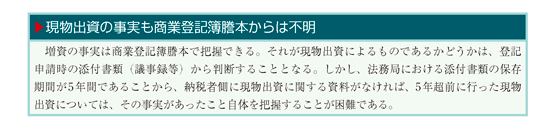
時間の経過により、法人税額等相当額控除の規制が事実上機能せず
実際に現物出資時の帳簿類が残されていないという問題は、平成6年の通達改正当時は問題にならなかったが、租税回避スキームが横行したバブル期から20年以上経過した今、それが顕在化し始めたわけだ。今回の事案もその1つと考えられ、評基通186−2の法人税額等相当額控除の規制が事実上機能しなくなってきたといえる。
同様事案が多数存在、他の事案への影響も
たとえば、いわゆるA社B社方式は、20年以上前のバブル期に数多くの金融機関や税理士によって利用された相続税(贈与税)の負担軽減スキーム。
株式等を贈与し、相続させることを目的として、法人税額等相当額控除の適用による相続税評価額圧縮のための「含み益」を恣意的に作り出したものの、平成6年の通達改正により、法人税額等相当額の控除ができなくなった。このため、贈与等を行うメリットがなくなってしまったものだ。
ただ、節税スキームが横行してから20年以上が経過した現在、結果として、帳簿類がなく現物出資時の相続税評価額がわからない株式等が多く現存する。
現時点での通達改正は未定
課税当局は、法律上の帳簿保存義務が経過したことにより、帳簿類が既に破棄されている場合の問題点を検討すべき事項として認識している。
しかし、現時点では具体的な検討までには至っていない。評基通186−2の改正も今のところ予定していない模様だ。
ただし、バブル期を中心に横行した租税回避スキームは、件数・金額ともに巨大であったし、現在「塩漬け」にされているその含み益が、今後発生する相続・贈与によって確実に表面化する。
今回の事案では、帳簿不存在以外にも個別の事情が可能性としては想定される。それでも今回の事案が他の同様事案に与える影響が大きいことに変わりはない。
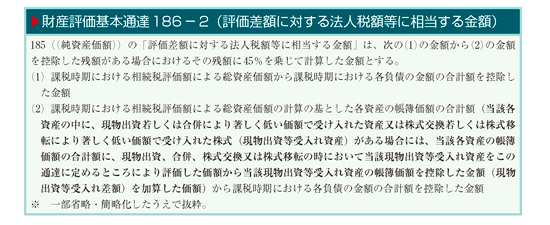
現物出資などを利用することにより、法人税額等相当額控除を恣意的に利用する租税回避スキームの1つがいわゆるA社B社方式である(図参照)。
具体的には、取引相場のない株式を純資産価額方式で評価をする際、評価差額に対する法人税額等相当額が控除できることに着目して、現物出資した取引相場のない株式の相続税評価額とその帳簿価額との評価差額を恣意的に作り出し、法人税額等相当額を控除することにより相続税評価額を約半分に圧縮することができた。
国税庁は、この租税回避スキームを問題視し、これを封じ込めるため、平成6年に評基通186−2の改正を行った。具体的には、評価会社が保有する資産のなかに現物出資(後の改正で合併、株式交換・移転に拡大)により著しく低い価額で受け入れた取引相場のない株式(後の改正で資産全般に拡大)がある場合、現物出資時の現物出資等受入れ資産の相続税評価額と受入れ帳簿価額との差額(現物出資等受入れ差額)から、法人税額等相当額が純資産価額の計算上控除できないこととされた。
なお、評基通186−2が改正される前の事案については、総則6項(評基通による評価が著しく不適当な場合、国税庁長官の指示を受け評価する旨規定)の適用により、個別具体的事案ごとに恣意的に作り出された評価差額に対する法人税額等相当額は控除しないとの取扱いがなされていた。
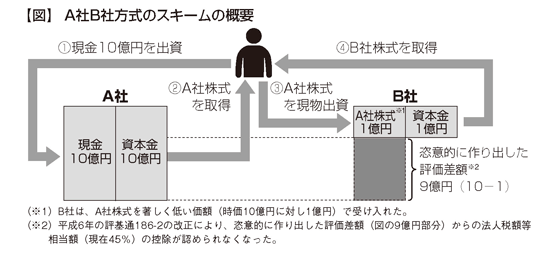 |
※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
⇒著作権等について
T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
キーワード 「45%」⇒48件
(週刊「T&A master」423号(2011.10.17「ニュース特集」より転載)
(分類:税務 2011.12.12 ビジネスメールUP!
1623号より
)
|